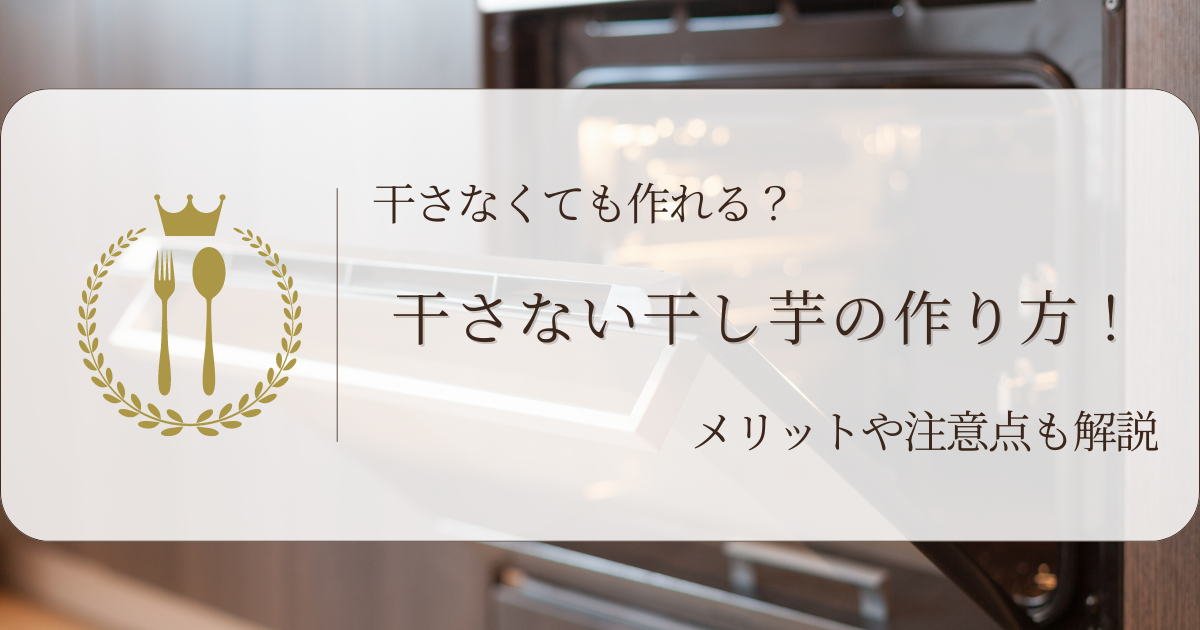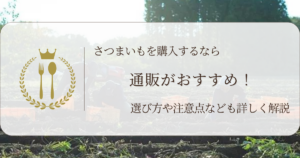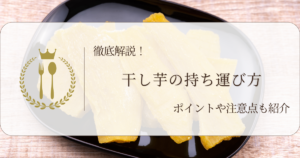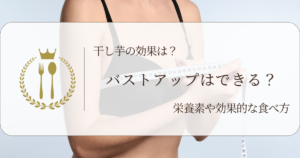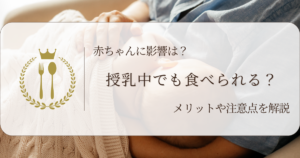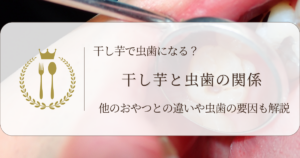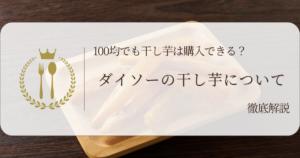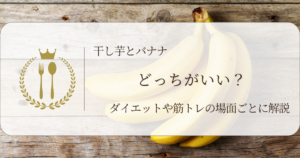「干し芋は干さなくても作れる」
「干し芋を干さずに作るメリットは?」
さつまいもが余っているから干し芋を作りたいけど、外で干すのは鳥や虫に食べられるかもしれないから避けたいという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、干さない干し芋の作り方について解説していきます。
また、干さずに作るメリットや注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者
フリー料理家兼調理学生
ゆるっとさわごはん🪴さん
「食 卓 に “ほっこり” す る 瞬 間 を」届ける料理系インスタグラマー。
Instagramのフォロワー数は8万人以上で、旬の野菜をシンプルに使ったじんわり沁みる優しさレシピを紹介中。

- 干さない干し芋の作り方
- 時短・衛生的などのメリット
- 作り方の手順と注意点
干さなくても干し芋は作れる?

干し芋は、必ずしも伝統的な天日干しの方法を用いなくても作ることができます。
調理技術や家電製品を活用することで、「干す」過程を省略しつつ、干し芋を作ることが可能です。
これらの方法では、さつまいもの水分を効率的に除去し、糖度を凝縮させることで、干し芋特有の甘みと食感を再現します。
オーブンや電子レンジなどの調理器具を使用することで、天候に左右されず、短時間で作ることができるのが大きなメリットです。
干さずに干し芋を作るメリット

干さずに干し芋を作る方法には多くのメリットがあります。
干さずに作ることで、従来の天日干しに比べて、効率的かつ安定した品質の干し芋を作ることが可能です。
ここでは、その具体的なメリットについて詳しく解説します。
- 時間が短縮できる
- 天候に左右されない
- 虫や鳥に食べられない
メリット①時間が短縮できる
干さずに干し芋を作る最大のメリットは、時間が大幅に短縮できることです。
天日干しでは数日から1週間以上かかることが一般的ですが、オーブンなどを使用することで、数時間から1日程度で干し芋を完成させることができます。
そのため、忙しい方でも手軽に干し芋を作ることができ、時間を有効に活用することが可能です。
また、短時間で作れるため、必要な時にすぐに干し芋を用意できる点も大きなメリットです。
これにより、家庭でのスナックや保存食として、いつでも新鮮な干し芋を楽しむことができます。
メリット②天候に左右されない
干さずに干し芋を作る方法は、天候に左右されないという大きなメリットがあります。
天日干しでは、晴天が続くことが必要であり、雨や曇りの日が続くと干し芋作りを中断しないといけないこともあるでしょう。
しかし、オーブンなどを使用することで、天候に関係なく安定して干し芋を作ることができます。
これにより、年間を通じて干し芋を作ることができ、季節や天候に左右されずに作業を進めることが可能です。
特に梅雨や冬季など、天候が不安定な時期でも安心して干し芋作りができる点は大きなメリットです。
メリット③虫や鳥に食べられない
干さずに干し芋を作るもう一つのメリットは、虫や鳥に食べられる心配がないことです。
天日干しは外で干すため、虫や鳥が寄ってきて干し芋を食べてしまうこともあるでしょう。
これにより、品質が低下したり、衛生面での問題が発生することがあります。
しかし、オーブンなどを使用することで、室内で干し芋を作ることができ、虫や鳥の被害を防ぐことができます。
そのため、虫や鳥の心配をせずに干し芋を作ることが可能です。
必要な材料と道具

干し芋を干さずに作るためには、適切な材料と道具を準備することが重要です。
これにより、効率的に高品質な干し芋を作ることができます。
ここでは、必要な材料とその選び方、および必要な道具について詳しく解説します。
- 必要な材料と選び方
- 必要な道具
必要な材料と選び方
干し芋を作るための主な材料は、さつまいもです。
さつまいもは、糖度が高く、肉質がしっかりしている品種を選ぶと良いでしょう。
特に「紅はるか」や「安納芋」などの甘みが強い品種がおすすめです。
選ぶ際には、表面に傷や腐敗がないものを選び、形が均一であるものを選びましょう。
大きすぎるものは切り分ける手間がかかるため、中くらいのサイズのものが理想的です。
また、さつまいもは新鮮なものを使用することで、美味しい干し芋を作ることができます。
購入後は、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管しておきましょう。
必要な道具
干さずに干し芋を作るためには、いくつかの専用の道具が必要です。
- さつまいもを均一にスライスするためのスライサー
- オーブン
- さつまいもを茹でるための大きな鍋
- さつまいもを蒸すための蒸し器
- さつまいもを冷やすラック
- ひっくり返すためのトング
まず、さつまいもを均一にスライスするためのスライサーがあると便利です。
スライサーを使うことで、手間を省き、均一な厚さに切ることができます。
次に、オーブンが必要です。
オーブンを使用する場合は、低温で長時間乾燥させることができるタイプを選びましょう。
また、さつまいもを茹でるための大きな鍋や、蒸すための蒸し器も必要です。
これにより、一度に多くのさつまいもを調理することができます。
さらに、さつまいもを冷ますためのラックや、乾燥中にひっくり返すためのトングも準備しておくと便利です。
干さない干し芋の作り方をSTEPごとに解説

干さない干し芋を作る時は、オーブンを利用することで短時間で効率的に行うことができます。
以下に、各ステップを詳しく解説しますので、参考にして高品質な干し芋を作りましょう。
さつまいもを水洗いする
まず、さつまいもをしっかりと水洗いします。
土や汚れが残っていると、干し芋の品質に影響を与えるため、ブラシなどを使って丁寧に洗い流しましょう。
特に皮の部分に土が付きやすいので、念入りに洗うことが重要です。
水洗い後は、さつまいもの表面の水気をしっかりと拭き取っておきます。
均等な大きさに切る
次に、さつまいもを均等な大きさに切ります。
スライサーを使用することで、厚さを均一に保つことができ、乾燥のムラを防ぐことができます。
手作業で切る場合は、包丁を使って5〜7mmの厚さにスライスするのが理想的です。
均一な厚さに切ることで、全体が均一に乾燥しやすくなります。
キッチンシートに並べる
スライスしたさつまいもをキッチンシートに並べます。
オーブン用の天板にオーブンペーパーを敷き、その上にさつまいもを重ならないように並べます。
さつまいもが重なると乾燥が均一にできないため、できるだけ間隔を空けて並べることが重要です。
この段階で、さつまいもが均等に並んでいるか確認しましょう。
オーブンを100℃に予熱し60分
オーブンを100℃に予熱し、さつまいもを入れて60分間乾燥させます。
低温でじっくりと乾燥させることで、さつまいもの甘みが凝縮され、美味しい干し芋が出来上がります。
オーブンの温度が高すぎると焦げる可能性があるため、100℃を保つことが重要です。
さつまいもをひっくり返す
60分経過したら、オーブンからさつまいもを取り出し、一枚一枚ひっくり返します。
これにより、全体が均一に乾燥し、ムラを防ぐことができます。
ひっくり返す際には、トングやフォークを使って丁寧に行い、さつまいもが崩れないように注意します。
再び100℃で60分
再びオーブンに戻し、同じく100℃でさらに60分間乾燥させます。
この段階で、さつまいもがしっかりと乾燥し、干し芋らしい食感が出てきます。
オーブンの中で均一に乾燥させるため、途中でオーブンの位置を変えることも効果的です。
好みの硬さになっていれば完成
最後に、さつまいもが好みの硬さになっていれば完成です。
オーブンから取り出し、冷ましてから保存容器に入れます。
冷蔵庫で保存することで、長期間美味しく食べることができます。
干し芋の硬さは個人の好みによるため、途中で確認しながら調整することがポイントです。
干さずに干し芋を作る時の注意点

干さずに干し芋を作る際には、いくつかの注意点を押さえることで、美味しい干し芋を作ることができます。
以下に、特に重要な注意点を解説します。
- 加熱し過ぎると硬くなってしまうことがある
- 干して作る干し芋と食感が異なる場合がある
- 均等に厚さを切り揃える必要がある
加熱し過ぎると硬くなってしまうことがある
干さずに干し芋を作る際には、加熱時間と温度に注意が必要です。
オーブンや乾燥機を使用する場合、温度が高すぎたり加熱時間が長すぎると、さつまいもが乾燥しすぎて硬くなってしまうことがあります。
これを防ぐためには、オーブンの温度を100℃程度に設定し、途中でさつまいもの状態を確認しながら加熱することが重要です。
特に、乾燥の後半では頻繁にチェックし、必要に応じて加熱時間を調整することで、理想の柔らかさと食感を保つことができます。
干して作る干し芋と食感が異なる場合がある
干さずに作る干し芋は、天日干しで作る干し芋とは食感が異なる場合があります。
天日干しでは、自然の風と日光によってゆっくりと水分が抜けるため、独特の柔らかさとしっとり感が生まれます。
一方、オーブンや乾燥機を使用する場合は、短時間で水分が抜けるため、やや硬めの食感になることがあります。
この違いを理解し、自分の好みに合わせて調整することが重要です。
例えば、オーブンでの加熱時間を短くすることで、柔らかい食感に近づけることができます。
均等に厚さを切り揃える必要がある
干さずに干し芋を作る際には、さつまいもを均等な厚さに切り揃えることが重要です。
厚さが揃っていないと、乾燥のムラが生じ、部分的に硬くなったり、逆に乾燥が不十分でしっとりしすぎる部分ができてしまいます。
スライサーを使用することで、均一な厚さにスライスすることができ、乾燥のムラを防ぐことができます。
手作業で切る場合は、包丁を使って慎重に切り揃え、5〜7mm程度の厚さにするのが理想的です。
これにより、全体が均一に乾燥し、理想の干し芋を作ることができます。
干し芋の干さない作り方についてよくある質問

干さずに作る干し芋に関しては、いくつかのよくある質問があります。
ここでは、具体的な質問とその回答を解説します。
干し芋で食卓と人生を豊かに

干し芋は茨城県の代表的な特産品ですが、照沼では約50ヘクタールの自社農園で主に紅はるかを生産し、自社工場にて干し芋の加工から販売までを自社管理のもと行っています。
また、食の安心安全や環境への配慮のため取組んでいる「農薬・化学肥料を使わない干し芋生産」の規模としては国内トップクラスです。
最近の干し芋需要の高まりを受けて、照沼の干し芋も各種メディアや著名人に取り上げていただき、日本最大級のさつまいも品評会である日本さつまいもサミットにて「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。
干し芋は家族・友人や大切な方へのギフト商品として、また日常食として定期購入される方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ照沼の干し芋・さつまいも商品をお試しください。
品質にこだわった照沼の干し芋で、食卓と人生を豊かにするお手伝いができれば幸いです。
干さなくても干し芋を作ることはできる
この記事では、干さない干し芋の作り方について紹介してきました。
干し芋は干さずに作ることもできますが、天日干しで作られた干し芋とは食感が異なる場合があります。
しかし、虫や鳥に食べられる心配がなかったり、時間が短縮できたりと干さずに作るメリットも様々なものがあります。
そのため、一度どちらの方法も試してみて、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。