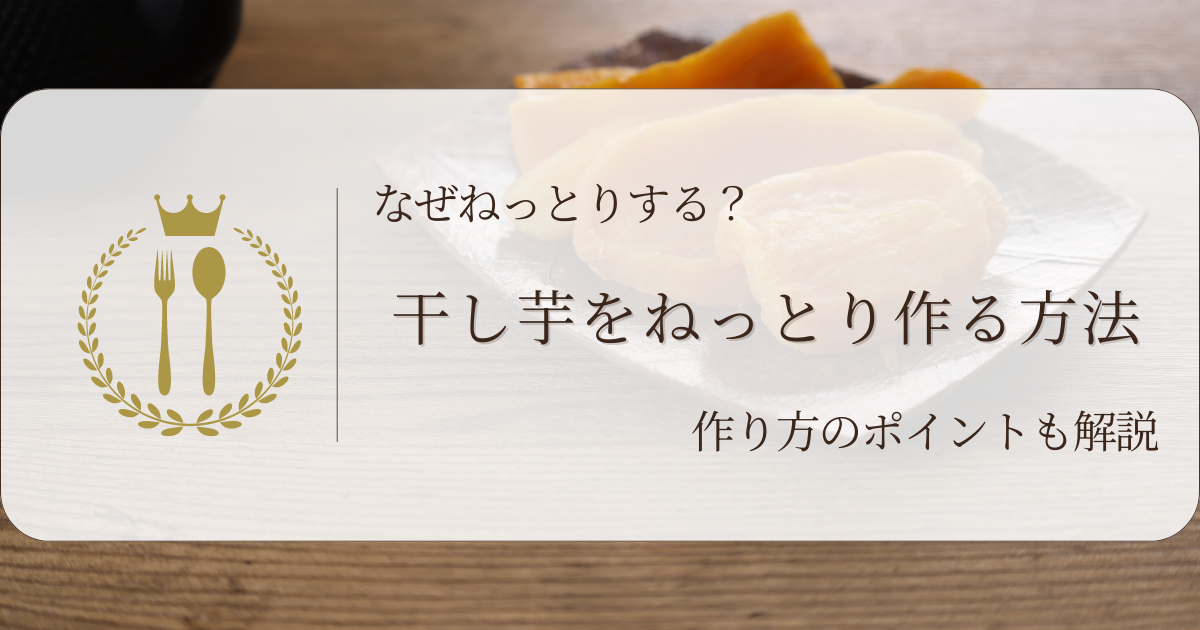「干し芋はなぜねっとりする?」
「ねっとり干し芋は自宅でも作れる?」
干し芋を自宅で作りたい方の中には、専門店のようなねっとり干し芋を作りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ねっとり干し芋を作る方法について紹介していきます。
干し芋はなぜねっとりするのかということや、ねっとり干し芋を作るポイントについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者
とり肉料理研究家
やぁ┋とり肉ダイエットめしさん
Instagramフォロワー6.8万人超の「飽きない!とり肉アレンジレシピ」考案者。双子ママのとり肉料理研究家として、美味しく健康的なダイエットをサポート。旦那の食事改善で7ヶ月20kg減量を実現。食品衛生責任者の資格を持ち、安全で栄養バランスの取れた簡単レシピを提案中。
干し芋はなぜねっとりする?

干し芋は、その独特の甘さとねっとりした食感で人気のある食品です。
このねっとり感は、さつまいもの品種と加工方法によって生まれます。
干し芋がねっとりな理由
干し芋がねっとりする理由は、さつまいもの品種と加工方法にあります。
特に、紅はるかや安納芋などのねっとり系の品種は、糖度が高く、繊維が少ないため、干し芋に適しています。
これらの品種を蒸してから乾燥させることで、デンプンが糖に変わり、甘味が増すのです。
この過程で、さつまいもの水分が適度に残り、ねっとりとした食感が生まれます。
また、干し芋を作る際には、天候や湿度に注意し、適切に管理することで、理想的な食感を得ることができます。
昔の干し芋はパサパサだった?
昔の干し芋は、現在のものと比べるとパサパサしていたと言われています。
これは、当時のさつまいもの品種や干し方が影響しています。
昔は、ホクホク系のさつまいもが主流で、水分が少ないため、干し芋にすると硬くなりがちでした。
また、保存性を高めるために長時間干されることが多く、その結果、パサパサした食感になっていました。
現代では、ねっとり系やしっとり系の品種が多く使われ、干し時間も適切に調整されるため、柔らかく甘味のある干し芋が主流となっています。
ねっとり干し芋を作るポイント3つ

ねっとりとした食感が魅力の干し芋。
その美味しさの秘密は、製造過程にあります。
ねっとり干し芋を作るポイントは主に3つあり、それぞれが重要な役割を果たしています。
- 干す時間(加熱時間)
- さつまいもの品種
- 保存方法
これらのポイントを押さえることで、家庭でも美味しいねっとり干し芋を作ることができます。
それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
①干す時間(加熱時間)
干し芋の食感を決める重要な要素が、干す時間と加熱時間です。
まず、さつまいもを蒸すか茹でる際は、中心まで十分に火を通すことが大切です。
これにより、デンプンが糖化しやすくなります。
その後の乾燥過程では、ゆっくりと時間をかけて水分を抜くのがポイントです。
急激に乾燥させると表面が固くなってしまうので、一般的に、50℃前後の低温で24〜48時間ほど乾燥させるのが理想的です。
②さつまいもの品種
ねっとり干し芋を作るには、適切なさつまいもの品種選びが欠かせません。
特に適しているのは、紅はるか、シルクスイート、安納芋などのねっとり系やしっとり系の品種です。
これらの品種は、もともと水分量が多く、糖度も高いため、干し芋にした際にねっとりとした食感になりやすいのが特徴です。
また、これらの品種は繊維質が少なく、肉質がなめらかなため、乾燥させても柔らかい食感を保ちやすくなります。
一方、ホクホク系の品種は水分量が少なく、乾燥させるとパサパサした食感になりやすいため、ねっとり干し芋には適していません。
③保存方法
ねっとり干し芋の美味しさを長く保つには、適切な保存方法が重要です。
乾燥後の干し芋は、湿気を吸いやすいため、密閉容器に入れて冷蔵庫で保存するのが理想的です。
ただし、完全に密閉すると結露の原因となりカビが生えてしまうので、少し隙間を作るか、乾燥剤を一緒に入れるとよいでしょう。
また、長期保存する場合は冷凍保存がおすすめです。
冷凍することで、ねっとりとした食感と甘みを長期間維持できます。
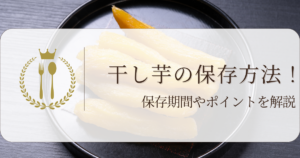
ねっとり干し芋を作るための準備

ねっとりとした食感が魅力の干し芋を作るには、適切な準備が欠かせません。
まず、良質なさつまいもを選ぶことが重要です。
さらに、必要な道具を事前に揃えることで、スムーズに作業を進めることができます。
- さつまいもを用意する
- 干し芋作りに使用する道具の用意
さつまいもを用意する
ねっとり干し芋を作るには、適切なさつまいもを選ぶことが重要です。
まず、形が整っていて傷みが少なく、太めのさつまいもを選びましょう。
均等に乾燥させるためにも、大きさがそろったものが理想的です。
さつまいもを購入したら、よく洗って土を落とします。
皮付きのまま蒸すので、皮をむく必要はありません。
蒸す前に、さつまいもを一晩程度常温に置いておくと、さつまいもに含まれるデンプンが糖化するので、より甘みが増すと言われています。
おすすめの品種は紅はるか
干し芋作りに最適な品種として、「紅はるか」がおすすめです。
紅はるかは、水分量が多く、糖度も高いため、ねっとりとした食感の干し芋に仕上がります。
また、しっとりとした質感と強い甘みが特徴で、干し芋にした際に美味しさが際立ちます。
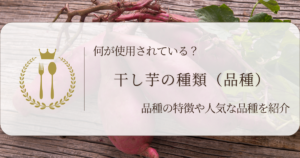
干し芋作りに使用する道具の用意
干し芋作りには、以下の道具を準備しましょう。
蒸し器:さつまいもを蒸すのに使用します。
竹串:さつまいもの加熱具合を確認するのに便利です。
軍手やふきん:熱いさつまいもを扱う際に使用します。
包丁とまな板:さつまいもを切るのに必要です。
干し網やザル:さつまいもを干す際に使用します。
また、天日干しの場合は、日よけや虫除けのためのネットも用意すると良いでしょう。
オーブンを使用する場合は、オーブン用の天板も必要です。
これらの道具を事前に揃えておくことで、スムーズに干し芋作りを進めることができます。
ねっとり干し芋の作り方をSTEPごとに解説

ねっとり干し芋を作るプロセスは、いくつかの重要なステップに分けられます。
各ステップを丁寧に行うことで、美味しい干し芋を作ることができるでしょう。
さつまいもを洗うことから始まり、加熱、皮むき、切り分け、そして乾燥まで、それぞれのステップが最終的な仕上がりに大きく影響します。
以下に、各ステップの詳細を解説していきます。
さつまいもを丁寧に水で洗う
さつまいもの表面に付着している土や汚れを丁寧に洗い落とします。
流水でよく洗い、必要に応じてブラシを使用して表面をこすります。
特に凹凸のある部分や芽の周りは注意深く洗い、洗浄後は、清潔なタオルで水気を拭き取りましょう。
さつまいもを茹でる or 蒸す
さつまいもを加熱する方法には、茹でる方法と蒸す方法があります。
蒸す方法がより一般的で、水分の調整がしやすいため推奨されます。
蒸し器に水を入れ、沸騰したら皮付きのさつまいもを入れます。
中サイズのさつまいもなら約30分程度蒸します。
竹串を刺してスッと通れば、中まで火が通った証拠です。
粗熱を取って皮を剥く
蒸し上がったさつまいもは、すぐに皮を剥くと火傷の危険があるため、粗熱を取りましょう。
手で触れる程度まで冷めたら、皮を剥きます。
皮は手で簡単に剥くことができますが、必要に応じて包丁を使用してもよいでしょう。
この時、さつまいもの表面を傷つけないよう注意します。
皮を剥いたさつまいもがまだ温かいうちに、切る工程に移りましょう。
均等な厚さに切る
皮を剥いたさつまいもを、均等な厚さに切りましょう。
一般的には5〜7mm程度の厚さが適しています。
均等に切ることで、乾燥ムラを防ぎ、仕上がりが均一になります。
縦長に切るか、輪切りにするかは好みで決めてください。
切る際は、切れ味の良い包丁を使用し、できるだけ同じ大きさと厚さになるよう心がけることが重要です。
天日干し or オーブンで加熱
最後の乾燥工程には、天日干しとオーブン乾燥の2つの方法があります。
天日干しの場合、天気の良い日に風通しの良い場所で2〜3日程度干しましょう。
虫よけのネットをかけるのを忘れずに。
途中で乾燥具合を確かめるために、こまめにチェックするようにしましょう。
完成した干し芋は冷めてから保存容器に入れ、冷蔵庫で保管します。
干し芋をさらにねっとりさせる方法

ねっとりとした食感が魅力の干し芋ですが、さらにねっとりとした食感を楽しみたい方もいるでしょう。
実は、干し芋の製造過程や食べ方を工夫することで、より一層ねっとりとした食感を引き出すことができます。
ここでは、さつまいもの貯蔵方法と食べる直前の温め方という2つのポイントに焦点を当て、干し芋をさらにねっとりさせる方法を詳しく解説します。
- さつまいもを貯蔵してデンプンを糖に変える
- 食べる前に少し温める
さつまいもを貯蔵してデンプンを糖に変える
干し芋の美味しさは、さつまいもの貯蔵段階から始まります。
収穫直後のさつまいもは、実はあまり甘くありません。
これは、さつまいもの主成分がデンプン質ですが、適切な条件下で貯蔵することで、このデンプンが糖に変化し、さつまいもの甘みが増していきます。
最適な貯蔵条件は、温度13〜15℃、湿度90%程度の環境です。
このような条件下で約2カ月以上貯蔵することで、さつまいもは熟成し、甘みが増していきます。
この過程で、デンプンがショ糖などの甘い糖分に変化し、もともと含まれている糖分も増加します。
食べる前に少し温める
干し芋をさらにねっとりとした食感で楽しむには、食べる直前に少し温めるという方法があります。
これは、干し芋に含まれる糖分の特性を利用した方法です。
干し芋には、麦芽糖、ショ糖、果糖、ブドウ糖などの様々な糖分が含まれています。
これらの糖分は、温度によって溶け方や粘性が変化します。
干し芋を少し温めることで、これらの糖分が溶け始め、よりねっとりとした食感が生まれるのです。
▶︎温め方を見る
温め方としては、電子レンジで10〜15秒程度加熱する方法が簡単です。
ただし、加熱しすぎると水分が蒸発してしまうので注意が必要です。
また、オーブントースターで軽く温める方法もあります。
この場合、表面が少し焦げ目がつく程度に温めると、香ばしさも加わって美味しく食べられます。
温めた干し芋は、糖分が溶けてより甘みを感じやすくなり、口の中でとろけるような食感を楽しむことができます。
特に冷蔵保存していた干し芋を食べる際は、この方法を試してみると良いでしょう。
ねっとり干し芋についてよくある質問

ねっとり干し芋は、その独特の食感と甘さで多くの人に愛されています。
ここでは、ねっとり干し芋に関するよくある質問とその回答をまとめました。
干し芋で食卓と人生を豊かに

干し芋は茨城県の代表的な特産品ですが、照沼では約50ヘクタールの自社農園で主に紅はるかを生産し、自社工場にて干し芋の加工から販売までを自社管理のもと行っています。
また、食の安心安全や環境への配慮のため取組んでいる「農薬・化学肥料を使わない干し芋生産」の規模としては国内トップクラスです。
最近の干し芋需要の高まりを受けて、照沼の干し芋も各種メディアや著名人に取り上げていただき、日本最大級のさつまいも品評会である日本さつまいもサミットにて「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。
干し芋は家族・友人や大切な方へのギフト商品として、また日常食として定期購入される方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ照沼の干し芋・さつまいも商品をお試しください。
品質にこだわった照沼の干し芋で、食卓と人生を豊かにするお手伝いができれば幸いです。
ねっとり干し芋で日々のおやつ時間を楽しもう
この記事では、ねっとり干し芋の作り方やそのポイントを紹介してきました。
作り方に気をつけることで、自宅でもねっとり干し芋を作ることができます。
特に乾燥具合には気をつけましょう。
乾燥の途中でこまめにチェックすることで、ねっとり干し芋を楽しむことができるでしょう。